Departments学科の特色
Department of International Studies
国際コミュニケーション学科
貧困や差別、紛争、気候変動など、世界は多くの課題に直面しています。今、求められているのは、これらの問題を的確に分析するとともに、異なる生活様式や世界観を持つ人々と理解しあい、文化の違いを超えて交流する能力を培うことです。本学科では、外国語(英語・中国語)、グローバルおよび地域の問題や異文化理解を学ぶ科目に加え、ヨーロッパ、中国、東南アジア、アフリカ、そして地元多摩での体験重視のプログラムを豊富に設けています。留学(長期・短期)する学生も多く、グローバル時代にふさわしい力を鍛えていく環境があります。

01講義はすべてアクティブラーニング
大学の講義といえば、「ノートを取りながら、ひたすら教授の話を聞く」といったイメージがあるかもしれません。今でもそういう授業が普通に行われている大学は珍しくありませんが、国際コミュニケーション学科の授業はまったく違います。教室で行われるすべての講義はアクティブラーニング形式で実施され、どの授業にもグループディスカッションやプレゼンテーションなどの活動が必ずと言って良いほど組み込まれています。講義を聴く·個人で考える·ペアやグループで話し合う·クラス全体でに発表する·自分の意見を小レポートで表現する、などの一連の活動からなる授業は、話を聞くだけの受け身の学習のまさに正反対。日常的な授業を通して、自ら考え、他者と協働しながら行動する人を育てていきます。

02世界と多摩でグローバル·コンピテンシーを鍛える
国際コミュニケーション学科では、世界の様々な人々と直に交流する実践的な学びを何よりも大事にしています。ヨーロッパ、中国、マレーシア、アフリカで行う「フィールドワーク」という授業には、毎年大勢の学生が参加しています。また、多摩地域をはじめとする日本国内における多文化共生をテーマとしたフィールドワークや、世界各国からやってくる国際ボランティアの若者たちとコラボして、地元の子どもたちに英語を楽しく学ぶ機会を提供する「サマースクール」、長編ドキュメンタリー映画を日本語に翻訳して字幕をつけて上映会を催す「映像翻訳」など、地域密着のプロジェクト型授業も盛んです。こうした実践型授業の充実したラインナップは、他大学に類例を見出すのが難しいほどです。

03留学制度(短期·長期)
明星大学は、世界中に40校を超える海外学術交流提携校を持っています。これらの大学への半期留学(前期または後期)では、留学中の学習成果に応じて本学の単位を認定する仕組みが整っており、休学することなく、4年間で無理なく大学を卒業することが可能です。また、近年では、夏休み·春休みを利用した短期留学(海外語学研修·海外研修·海外インターンシップ)も人気です。中には、韓国への短期留学で韓国語を集中的に学習し、ハングルで書かれた学術論文を読みこなすことができるようになる学生も。

04先輩たちが歩んでいる道
高度なコミュニケーション能力を備えた人材は、社会のさまざまな分野での活躍が期待されます。毎年多くの卒業生が、金融関係(証券会社、信用金庫など)、メーカー、エネルギー関連企業、IT企業、旅行·宿泊関連企業、小売業、物流関連企業、中学校·高等学校の英語教諭などに就職しています。また、小学校教員免許プログラムを利用することで,小学校教諭になることも可能です。また、卒業生の中には、国連職員や、JICA海外協力隊員として発展途上国で活躍している先輩たちもいます。
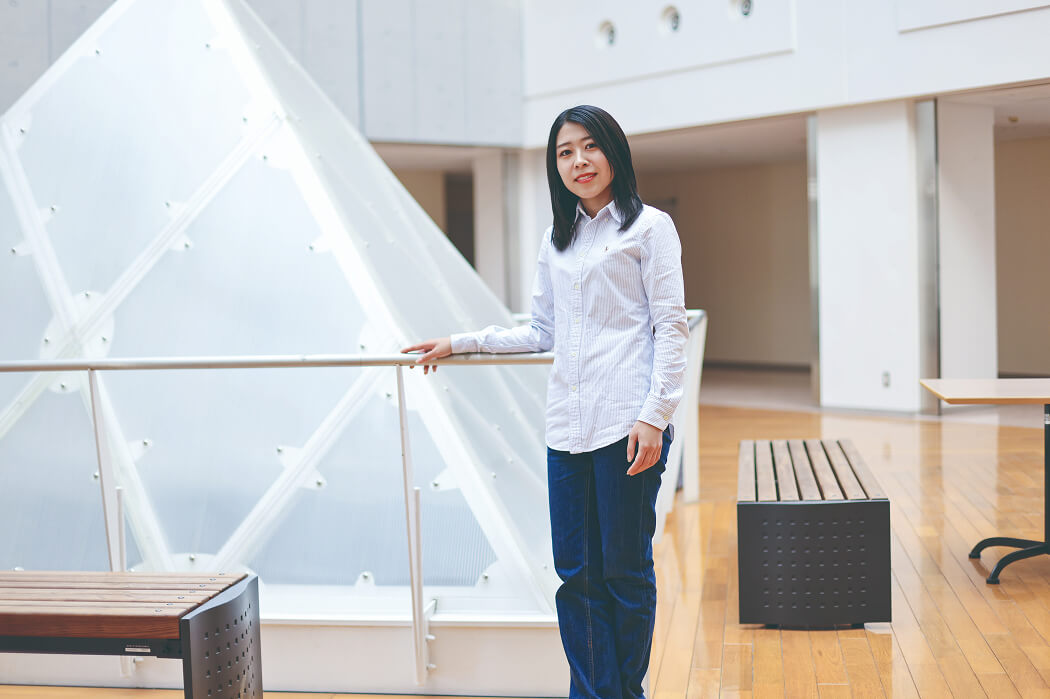
資格取得
中学校教諭一種免許状(英語)、高等学校教諭一種免許状(英語)、学校図書館司書教諭、図書館司書の免許·資格が取得可能です(2025年4月現在の予定)。ただし、免許·資格の組み合わせにより、4年間で同時に取得できない場合があります。
カリキュラム表
カリキュラム表ダウンロードDepartment of Japanese and Comparative Culture
日本文化学科
日本文化を正しく理解し、世界に発信できる人材を養成。
マンガ、アニメ、小説、映画、食など、幅広い分野で世界中から人気を集める日本の文化について、日本人自身が理解を深めることで、世界に発信できる力を身につけます。

01学びの特長
- 学生の興味を否定しません「ラノベやアニメは低俗だからは卒論にはならない」…こんな考えは、本学科の教員には一切ありません。我々は、学生の興味に寄り添い、研究として成立するためのサポートをします。ただし、楽だということではありません。調査方法やまとめ方はしっかり指導します。
- 豊富な体験教育を提供します「体験教育」は、明星学苑全体の創立以来の教育方針の一つです。日本文化学科ではホンモノの体験を通じて日本文化を理解するプログラムを数多く用意しています。
- 言葉の力を鍛えます自らの興味を深める鑑賞力、社会に求められるコミュニケーション能力、すべての根幹は言葉の力です。本学科の授業は、読み書きだけでない多様な言葉の力を育みます。

02学びの流れ
1年生の時には、日本語を磨き、さまざまな文化を体験をし「好き」の視野を広げ、2年生の時にはさまざまな学びを通して個々の興味関心に合う分野を発見します。3年生になると、演習や議論を通して、日本文化を深く読み解きながら自身を磨き、4年生では、自身のテーマに沿って卒業演習に取り組み、卒業論文として成果の発信を行います。

03日文研究会
授業を超えた学びのサークル、それが日文研究会です!「国語科教職研究会」「歴史を旅する会」「美術・視覚文化研究会」など様々な会が用意されています。
学科の教員が提示するテーマに基づき、学生が中心になり日々活動しています。
また、日文研究会では、ただ学習するだけではなく、日本文化の発信を重視しています。結果、発信力が身につきます。

04就職実績
一般企業、公務員、教員をはじめ、幅広い就職実績があります。国語科教員や編集・印刷出版業・広告業など日本語表現に深くかかわる職業はもちろん、金融業・製造業・小売業などの一般企業など、多様な企業で卒業生が活躍しています。日本文化学科で身につく、日本語運用能力をベースとした「資料や情報を理解する」「調べた内容をまとめる」「わかりやすく伝える」スキルは、卒業後も社会人としての基礎的な力へ直結します。

資格取得
日本文化学科では次のような資格を取得することができます。
-
中学校・高等学校教諭一種免許状(国語)
本学科では伝統的にもっとも目指す学生が多い資格です。毎年多くの学生が資格を取得し、近年とくに教員に採用される学生が増えています。
-
博物館学芸員
学芸員にあこがれる学生も多く、志望者の多い資格です。日本文化学科には学芸員資格を持った実習指導員がおり、さまざまなアドバイスを受けることができます。
-
図書館司書
図書館司書を将来の夢と考える学生も少なくありません。司書の資格をとることでその夢に近づきます。
-
学校図書館司書教諭
学校図書館を担当する教員に必要とされる資格で、国語科教員免許と一緒にとる学生が多いようです。
-
社会教育主事任用資格
「社会教育主事」とは、自治体の教育委員会に置かれる専門職員で、社会教育を行う者に対する専門技術的な助言、指導をする役割です。
カリキュラム表
カリキュラム表ダウンロードDepartment of Sociology and Human Welfare
人間社会学科
人間関係や家族などの身近なことから、国境を越えたグローバルなことまで、私たちが暮らす現代社会を幅広く探求します。フィールドワークやアンケート調査を行い、実践的に社会を見る目を鍛えます。社会学を軸に少人数制で学ぶゼミと自由度の高いカリキュラム構成で、将来に向けて、一人一人の学生がじっくりと自分の問題意識を掘り下げていける学習環境が整っています。

01学ぶテーマは、きっとあなたの中にある
人間関係や教育制度、就職難、環境問題、若者文化、地域格差など。私たちが暮らしている社会では、日々多くの問題が生まれます。それらのすべてが社会学のテーマです。人間社会学科では、身近な問題からグローバルな問題まで、幅広く学びます。学生の興味関心や、将来の夢に応じた4つのコースを設定し、一人一人が学びたいことを選べる環境を整えています。

02学生が自ら参加して創っていくゼミが充実
学生自らが調べ、発表し、学生の間で話し合い、教員も交えて活発なコミュニケーションのもとで進められていく、10人から15人程度の少人数で学ぶゼミが、1年生から4年生まで設けられています。学生と教員が近い距離で、顔を見える関係性を築きながら、学生一人一人の問題関心を丁寧に引き出しながら授業をおこなっています。
1年生の時には、ゼミの導入として「レポート作成とプレゼンテーション」や「フィールドワークの招待」などを行います。2年生から学びたいことに近いゼミに所属し、自分の問題意識を深めていきます。4年生では大学での学びの総決算として自分でテーマを決めて、卒業論文を書きあげます。

03実社会に学ぶ実践型授業の展開
社会は直接目にみえるものではありません。教室を飛び出して実際の現場に出向き、自ら調べて、話を聞いて、時にはともに身体を動かしながら学ぶ、フィールドワークをやる機会を豊富に提供しています。大学周辺のまち歩きをし身近な地域の再発見したり、多摩地域のコミュニティビジネスの活動に参加し現状と課題を探ったり、沖縄名護市辺野古に訪問し住民への聞き取りをしたりと、様々な場所でフィールドワークを実施しています。学びのフィールドを海外にも広げて展開するゼミもあります。「アンケートデータの分析法」や「アンケート調査実習」などを通じて、アンケートを自分たちで作成し、調査を実施して、結果を読み解く技量を身につける授業もあります。
さらに「ドキュメンタリー実習」などをつうじて、現場に出向き、映像に収めて、映像作品を制作する技が身につく授業も開設されています。

04卒業後の進路
人間社会学科では、社会学を道具に、わたしたちが生きている社会を見る目を養い、主体的に行動し、自分の人生を不断にデザインできる人を育てます。
卒業後の進路は、公務員や教員、さらに地域社会に根差した信用金庫をはじめ、学生の関心に応じて幅広い分野の民間企業に進むことができます。大学院などに進学をしたり、専門学校に進んで資格を得たりなど、さらに学びを深めることもできます。社会事業をおこなうNPOの分野で活躍したりすることもできます。
学科には専属のキャリアカウンセラーがいて、相談したり、卒業後の進路に向けたバックアップ体制が整っています。

資格取得
人間社会学科では、社会調査士の資格を取得することができます。社会調査士とはアンケート調査やインタビュー調査の手法を学んで社会調査を行う能力と、統計や世論調査の結果を読み解く能力とを備えた「社会調査の専門家」です。「一般社団法人 社会調査協会」の認定を受けた本学科の該当科目を履修・修得することで、卒業時に資格を得ることができます。社会分析の重要性が高まっている今、社会調査士は社会に必要とされる人材です。
また中学校の社会科、および高校の公民の教員免許も取得できます。社会学の知識を備えた、生徒たちの「生きる力」を育成できる社会科教員になることができます。そのほか、図書館司書、学校図書館司書教諭、社会教育主事任用資格の取得も可能です。
明星大学通信教育課程と併修することで、小学校の教員免許も取得することができます。

Department of Social Work
福祉実践学科
子育て支援や障害者雇用への支援の需要が高まる現在、社会のあらゆる分野で福祉の理念を実現できる人が求められています。福祉実践学科では、社会のニーズに応えて、児童、高齢、障害、精神保健や地域共生、マイノリティなど幅広い分野を複合的に学べるカリキュラムを設置。社会福祉士やスクールソーシャルワーカーなどの専門職はもちろん、一般企業でも福祉の知識を活かして活躍することができます。
01福祉の実践力を身につける!
子育て支援・障害者雇用支援・高齢者支援・まちづくり・商品開発・顧客対応など、社会のあらゆる分野で福祉の理念を実践できる人が必要とされています。福祉実践学科では、福祉専門職の資格取得に必要な科目だけでなく、海外福祉事情やマイノリティ、障害学といった幅広く複合的に学べる科目を履修し、フィールドワークや福祉施設・一般企業での実習やインターンシップを通して、福祉の実践力を高めることができます。
02多文化共生社会を支える
福祉職業人・福祉社会人を育成
学科では、「誰かの役に立ちたい」という思いを4年間かけて形にしていきます。体験を重視したカリキュラムに基づき、大学での講義だけでなくグループ学習やフィールドワーク、実習等の機会を通して、社会のさまざまな課題やニーズとその解決方法・多職種連携の方法を多面的に学びます。その過程で各自の適性を見出し、社会福祉士・スクールソーシャルワーカー等の福祉専門職や、一般企業で福祉の知識を生かして活躍できる人として社会に巣立っていってもらいたいと考えています。
03計画的な社会福祉士国家試験対策、
福祉実習指導室/国家試験対策室完備
学科では、1年生からの継続的な指導により自主的な勉強環境を醸成します。社会福祉士国家試験対策も4年間で計画的に目標達成できるメソッドが整っています。また、本学科では、福祉実習指導室/国家試験対策室を完備。ソーシャルワーク実習やインターンシップ、国家試験受験のために、学生自らが学びを深め、実務的な準備をおこなう場所となります。実習指導員が常駐し、各種連絡にあたるとともに、学習が円滑にすすみ、多くの実りが得られるよう側面から支援します。
04就職実績
福祉を学んだ学生の就職先は、社会福祉法人や福祉系の株式会社だけでなく、福祉系以外の民間企業にも広がっています。それは、さまざまな立場の人たちが地域の中で暮らし、社会参加することを支える場が広がり、福祉の知識や技術を有する人材が広く求められているからです。学科の卒業生たちは、それぞれの場で「人の役に立つ」ことを実践しています。
資格取得
福祉実践学科では、福祉専門職人として社会で活躍する時に必要な、社会福祉士国家試験受験資格、スクールソーシャルワーカー、児童福祉士任用資格、身体障害者福祉司任用資格、知的障害者福祉司任用資格、社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格が取得可能です(4年間で取得可能な資格の組み合わせには上限があり、別途実習費などが必要です)。社会福祉士の試験を受ける人のための対策講座もあります。また、一般企業に就職して福祉の知識を役立てたい人のために、福祉住環境コーディネーター2級・3級、手話技能検定3級・4級の資格取得支援を行っています。学生自身の目標やキャリア形成に向けてきめ細かい対応を行います。
カリキュラム表
カリキュラム表ダウンロード